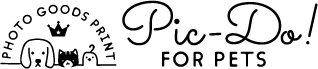自慢のペットの写真を誰かに見せたときに、「あなたに似てるね!」と言われた経験がある飼い主さんはいませんか?
顔や表情、行動など、なぜかペットが飼い主さんに似ることがあるようです。
今回はペットと飼い主が似ている理由などを詳しくご紹介したいと思います!
飼い主の生活の影響を受けている!?
人間でいうと、『似たもの夫婦』という言葉があります。長年生活を共にしていると、性格や表情が似ることがあるようですが、これはペットと飼い主の関係にも当てはまります。
なぜなら、飼い主の接し方によって、ペットが影響を受け、性格が形成される部分があるからです。
例えば飼い主が不安を感じると、ワンちゃんもそれに同調をしてくっついてきたり、傍を離れないことがあります。
ペットが真似をしている!?
犬は群れで暮らす動物であるため、基本的に誰かの真似をして生きている生き物です。例えば、野生であれば、親の真似をして獲物をとったり、兄弟たちで同じような動きをして遊んだりして生活をします。それと同じように、ペットも飼い主や同居する家族と、似たような行動を真似しているようです。
また、ペットは飼い主に同調しますので、不安やストレスを感じることが多い飼い主のペットは同じように落ち着きがなく不安定だったり、にぎやかな家のペットは活動的でにぎやかな性格になったりすることがあります。
自分と似ているペットを選んでいる!?
また、人間は見慣れたものを見ると落ち着く習性があるので、無意識に自分に似たペットを選んでいるのではないかと言われます。
性格や顔つき、生活リズムなど、自分に似た部分があるペットを選んでいるそうですよ!ペットと似ている、と言われるのも、無意識に顔立ちや表情が似ているワンちゃんや猫ちゃんを、ペットとして迎えているんですね。 もちろん、顔や性格が飼い主に似ているかどうかではなく、大事なペットですから、大事に可愛がってあげてくださいね!
いかがでしたか?今回は、飼い主とペットが似る理由についてご紹介しました。あなたとペットは、似ているところはあるでしょうか?♡