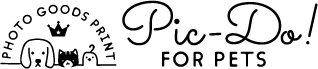たくさんの種類の猫がいますが、あなたはどの猫ちゃんが好きですか?どの子も違った可愛いさやかっこよさ、ぶちゃかわいさがあって選べませんよね~!今回は飼っている人が多い猫種トップ10の中から、3種類の猫ちゃんについて調べました♡
圧倒的多数♡ミックス
2種類以上の猫同士から生まれた混血種の「ミックス」は、日本で最も多く飼育されている猫種です。いわゆる「雑種」ですが、ペットショップなどではブリーダーによって純血同士を掛け合わせた種類のことを指します。日本でいうと、昔からなじみのある「三毛」や「トラ」がその代表です。ミックスは、純血種同士の子よりも遺伝的に丈夫な子が生まれやすい傾向にあります。また、親猫の身体的特徴や性格のどの部分を受け継ぐかは生まれるまでわからないので、きょうだいでも見た目が全然違う!なんていうことも。性格もルックスも多種多様なことが、ミックスの人気の理由ではないでしょうか。
お耳が可愛い♡スコティッシュ・フォールド
垂れ耳が特徴的なスコティッシュ・フォールドは、スコットランド生まれの猫です。短毛と長毛どちらもいますが、おそらく短毛種のほうがメジャーではないでしょうか。垂れ耳が特徴ではありますが、遺伝性疾患の観点から、現在は立ち耳のスコティッシュ・フォールドが全体の半分以上を占めているそうです。性格は人懐っこく、甘えん坊で大人しい子が多いので、初めて猫ちゃんを飼う人でも安心なのではないでしょうか。環境の変化にも強く、小さなお子さんがいるご家庭では飼いやすいと言われています。
人懐っこい♡アメリカン・ショートヘア
「アメショー」の愛称で人気のアメリカン・ショートヘアは、元々作物や船の荷物をネズミから守るワーキングキャットとして飼われていました。日本に入ってきたのは1980年以降で、丸顔に大きな丸い瞳が愛らしく、それでいて横長で角張っているマズルはキリッとした印象を与えます。人懐っこく賢いため、躾がしやすい反面、自立心が強いので付かず離れずの距離感が大事です。好奇心旺盛で動き回りイタズラ大好きなので、お迎えする場合はキャットタワーやキャットウォークなど、思いきり遊べる環境を用意してあげてくださいね♪
いかがでしたか?今回は、人気の猫ちゃん3種類についてご紹介しました。とっても可愛い猫ちゃんたち、どの子にも癒やされますね♡