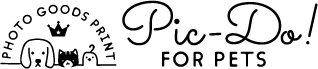夏は、暑さや湿気で人間にとっても過酷ですが、被毛を着ているワンちゃんにとってはとても危険な季節です。
特に、お散歩に出掛けるワンちゃんにっとて、気を付けたいのが熱中症ですね。
今回は、そんな大切なワンちゃんを熱中症から守るためのグッズを紹介したいと思います。
おすすめグッズ① 愛犬の熱中症チェッカー
地面に近いところを歩くワンちゃんは、人間よりも熱中症になりやすいことが知られています。
そこで、お散歩の際は、「熱中症チェッカー」を利用してみましょう。熱中症チェッカーは、熱中症に対する警戒指数で、ワンちゃんにとって温度や湿度が危険な状況になるとブザーで知らせてくれます。
もちろん、ブザーだけに頼らず、お散歩中にワンちゃんがふらふらしていたり、いつもより呼吸が荒かったり、よだれがよく出るなどの症状がないか気を付けて見てあげてください。
おすすめグッズ② クールベスト
クールベストは、暑い夏のお散歩にぴったりのアイテムです。
クールベストを水で濡らして、絞ったものを外出時に着せるだけなので使い方も簡単です。
特に暑い日には、10分ほど冷蔵庫で冷やしておくのがおすすめです。より快適にすごせますね!
気化熱で、水が蒸発するときに体温を下げるので、涼しさが持続します。水が全て渇いてしまっても、また濡らすと涼しさを感じるので、経済的です。
お散歩好きなワンちゃんにぴったりの一枚ですね♪
おすすめグッズ③ ペットスエット
水分補給はこまめにしてほしいけれど、あまりお水が好きではないワンちゃんもいますよね。そんなワンちゃんの水分補給にぴったりなのが「ペットスエット」です。
ワンちゃんの体のイオン組成に近い成分で、水分はもちろん、汗をかくと失われがちなミネラルも補給できます。
ペットボトルのドリンクタイプの他に、ゼリータイプもありますので、お散歩だけでなく、旅行やちょっとしたお出掛けに持って歩けるのも便利です。
いかがでしたか?今回は、ペットの熱中症対策におすすめのグッズをご紹介しました。飼い主さんも愛犬も、暑さ対策をしっかりして、夏を元気にすごしたいですね♪